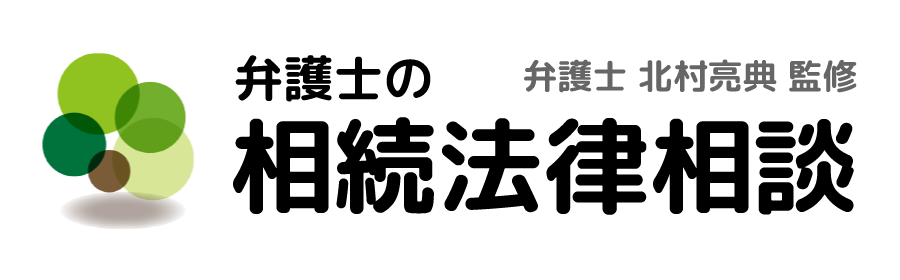Q 私には妻も子どももおらず、血のつながった家族は、兄がいるだけです。
したがって、私が死んだら私の財産は全て兄が相続することになります。
しかし、私は兄とは昔からとても仲が悪く、兄は私の婚約者との交際を邪魔したり、私が精神異常だといって精神病院に放り込んだりするなど、ひどいことばかりしてきました。
そんな兄に私の遺産を相続させることはとても抵抗があります。
そんな折、私が入院している病院でとても親しい友人ができました。
このまま私が死んで兄に遺産が行くくらいなら、その友人にいく方が良いと考え、その友人と相談して養子縁組することになりました。
このような養子縁組は後で無効とされることはないでしょうか。
A 単に相続が目的であって、親子関係を形成させる意思がない養子縁組は無効とされます
【以下、お読みになられる前に注意】*2017年2月7日追記
最高裁判所平成29年1月31日判決で、節税目的の養子縁組の有効性について、
「相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。」
と判断しました。
上記判断が、今後の養子縁組の有効性の判断に影響を及ぼす可能性があることにご留意いただき、以下お読みください。
養子縁組というのは、真に養親子関係を生じさせようとする意思(これを縁組意思といいます)によるものであることが必要です。
したがって、こうした意思を含まず、単に何らかの方便として養子縁組の形式を利用したに過ぎない場合は、縁組意思を欠くものとして、その養子縁組は無効とされます。
今回のように、単に相続が目的であって、親子関係を形成させる意思がない養子縁組は無効とされます。
もっとも、養子縁組というのは、縁組をした二人だけの間の出来事ですので、本人たちから「相続が目的なんかじゃない。」と言われてしまうと、外野から「相続が目的だから、養親子関係を生じさせようとする意思」がない等と言って無効を主張することはそれほど簡単ではありません。
あくまでも、
・両者の間に親子という身分関係の設定の基礎となるような人間関係は存在しているか
・養子縁組がされた後も、両者が親族として交流した形跡があるかどうか
という事実の有無が重要になるのです。
今回の事例は、名古屋高等裁判所平成22年4月15日判決の事例をモチーフにしたものですが、この事例では、本人が死んだ後に、兄が養子縁組無効の訴えを起こし、それが認められました。
この事例で裁判所は、
・本人とその友人は親しくなってからわずか4ヵ月後に養子縁組をしていること
・同居して生活していた期間も僅か4か月程度しかないこと
・その友人は、本人の死後、葬儀の香典を受け取りながら香典返しをせず、他方で、本人の遺産を費消して高級外車に乗り換えるなど散財行為に及んでいたこと
・本人は養子縁組をした時点で認知症の疑いがあったこと
等といった事情を考慮して、本件養子縁組は、養親子関係という真の身分関係を形成する意思はなく、兄への相続を阻止するための方便として、友人との養子縁組という形式を利用したにすぎないものと認められるから、無効である、と判断しました。
昔は、相続税を安くするために養子縁組が濫用されるという時代もあったようですが、いずれにしても、むやみやたらに養子縁組することはやめましょうということです。
2015年11月30日更新