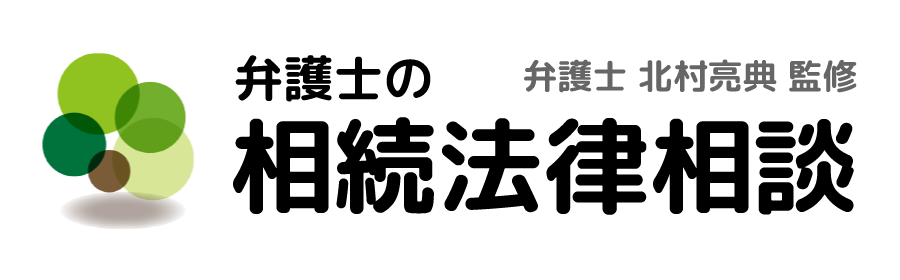【質問】
私の叔父が亡くなりました。
叔父は生涯独身で、私の親を含む叔父の兄弟姉妹も皆他界しており、相続人は甥と姪である私たちしかいません。
叔父の生前に、内縁の妻のような形で同居していた女性がいて、叔父の死後はその女性が葬儀などの手配も行い、遺骨も持っていっています。
私は、叔父の生前に「お前の親と同じ墓に入れてくれ」ということを言われていたため、この女性に対して遺骨の引渡しを求めたのですが、この女性は「私が供養する」と言って遺骨を渡してくれません。
どうしたら良いでしょうか。
【説明】
遺骨は、所有権の対象となると解されています。
そのため、人が死亡した場合に、その遺骨は誰が所有すべきか、という点が問題となります。
この点については、従来、遺骨は相続財産に該当するとか、祭祀承継者に帰属するとかなど、見解が分かれているところでしたが、最高裁平成元年7月18日判決において、「遺骨は慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属したとして、祭祀を主宰すべき者への遺骨の引渡しを命じた原審の結論を維持する」という旨の判断がなされています。
したがって、現在は、遺骨の所有権については、相続財産に該当せず、
「遺骨は慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属する」
という見解が裁判実務上は通説といえます。
そうなると、本件の事例においては、遺骨の引渡を求めるにあたっては、自らが祭祀承継者であると認められる必要があります(なお、本件の事例は、大阪家庭裁判所平成28年1月22日審判の事例をモチーフにしたものです)。
なお、この祭祀承継者については、民法897条に規定があります。
第897条
1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
「系譜」とは歴代の家長を中心に祖先以来の系統(家系)を表示するもの
「祭具」とは祖先の祭祀、礼拝に供されるもの(位牌、仏壇等)
「墳墓」とは遺体や遺骨を葬っている設備(墓石、墓碑等)
となります。
なお、被相続人の位牌については、被相続人の死亡後に作成されるものでありしたものであり、被相続人の祭祀財産には当たりません。また、被相続人の遺骨についても、生前の被相続人に属していた財産ではないため、相続財産を構成するものではなく、また、民法897条1項本文に規定する祭祀財産にも直接には該当しないとされています。
もっとも、遺骨についての権利は、通常の所有権とは異なり、埋葬や供養のために支配・管理する権利しか行使できない特殊なものであること、既に墳墓に埋葬された祖先の遺骨については、祭祀財産として扱われていることなどを理由として、被相続人の遺骨について、その性質上、祭祀財産に準じて扱うのが相当である、というのが裁判所の考え方です(大阪家裁平成28年1月22日より抜粋)。
したがって、被相続人の指定又は慣習がない場合には、家庭裁判所は、被相続人の遺骨についても、民法897条2項を準用して、被相続人の祭祀を主宰すべき者、すなわち遺骨の取得者を指定することができると言うことになりますので、遺骨の引渡を求めるためには、家庭裁判所に祭祀承継者指定の審判の申立をする必要があります。
なお、家庭裁判所が祭祀承継者を指定するにあたっては、
「被相続人との身分関係や生活関係、被相続人の意思、祭祀承継の意思及び能力、祭具等の取得の目的や管理の経緯、その他一切の事情を総合して判断」されます。
本件の大阪家裁の事例では、被相続人の生前の生活関係等から甥よりも同居している女性の方が緊密であったとして、当該女性を祭祀承継者と指定しています。
2018年5月20日更新