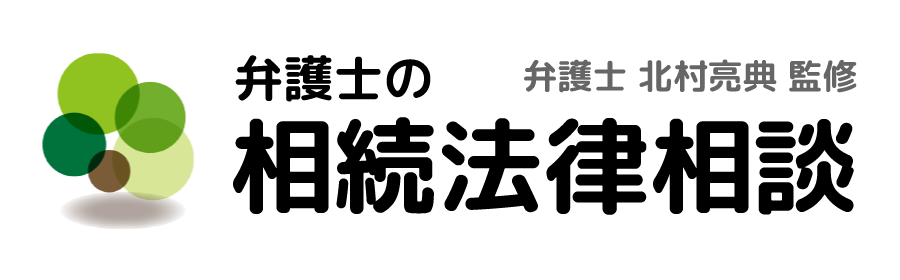遺言を作成した当時、遺言者が認知症を患っていた場合、
「遺言者には遺言能力がなかった」
として、後に訴訟でその遺言の効力が争われることがあります。
「遺言能力」とは、単純にいえば、その本人が遺言の内容をしっかり理解できるだけの知的判断能力があったかどうか、ということです。
重度の認知症の老人の方が遺した遺言書では、この遺言能力が否定されるケースが多いです。
公証人が立ち会って作成する公正証書遺言の場合も、この遺言能力を問題として争われるケースは多く、「公正証書遺言」であっても、遺言能力がなかった、として無効とする裁判例も多く存在しています。
でば、どのような場合に、「公正証書遺言」が無効とされているのでしょうか。
遺言能力の判断に当たっては
・遺言者の年齢
・当時の病状
・遺言してから死亡するまでの間隔
・遺言の内容の複雑さ(本人に理解できた内容であったか)
・遺言者と遺言によって贈与を受ける者との関係
等が考慮されますが、上記の要素を判断するにあたって一番重要なのは、遺言を書いた時と近い時点での「医師等による診断結果」です。
医師による鑑定結果を踏まえて、公正証書遺言を無効とした裁判例として、高知地方裁判所平成24年3月29日判決のケースがあります。
このケースは、遺言者について
平成17年9月9日 医師により財産管理能力がないという鑑定書の作成
平成17年10月12日 公正証書遺言作成
平成17年11月2日 遺言者について成年後見開始の審判
という事実経過を辿っており、そもそも認知能力(遺言能力)がかなり怪しい事案ですが、それでも公正証書遺言が作成されていたという事案です。
この事案について、医師は鑑定書において以下の指摘をしました。
①アルツハイマー型認知症を発病しており,程度は中等度以上である。
②自己の財産を管理・処分する能力はない。
③回復の可能性は極めて低い。
④記憶力
氏名・生年月日は正確に答える。既時型記憶力は多少保たれており,数列の逆唱は可能である。しかし,近時記憶は著しく障害されている。遅延再生試験が全くできない。遠隔記憶の障害も出現しており,夫の死亡時が分からない,同胞の名前や出生順があやふやなどの症状が見られる。
⑤見当識
時間的な見当識,場所の見当識が障害されている。時間的なものについては現在の年月日,曜日のいずれも分からない。場所的なものについても,現在いるところが自宅でないことは分かっているが,勤務先と思っている。人についての見当識は保たれている。
⑥知能検査,心理学的検査
長谷川式スケール 13点
⑦説明
本人は,平成14・5年頃より短期記銘力低下による症状(物盗られ妄想,火の不始末等)が出現。骨折による入院のため環境が変化したことで,その症状が増悪し,時間・場所の失見当識もこれに加わってきている。これらは一時的な意識レベルの障害であるせん妄や,精神疾患であるうつ病によるものではない。(中略)本人はアルツハイマー型認知症を発病していると考える。遠隔記憶の障害が始まってきており,時間だけでなく場所の失見当識もみられ,また物盗られ妄想が強く不穏もみられることより,その程度は中等度以上であると考える。
食事や排泄等,ADLは見守りから一部介助の状況であるが,近時記憶の著しい障害により,社会生活上,状況に応じた合理的な判断を下すことは不可能であろうと思われる。このため,自己の財産を管理・処分する能力はないと思われる。
また,これらの症状は,発症時より進行を続けており,現代の医療では回復していく可能性は極めて低いと考える。
上記のような医師の鑑定結果を踏まえて、裁判所は以下のとおり判断して、公正証書遺言を無効としました。
「ア I医師は,平成17年9月9日,亡A1には財産を管理する能力がないとの鑑定意見を作成しているが,この鑑定が,それまで半年以上の長期間にわたり亡A1の診察に当たってきた医師によるものであることや,その内容が合理的かつ説得的であること,そして,その鑑定結果に基づいて実際に成年後見開始の審判がなされたことなどを考慮すると,その鑑定結果には高度の信用性が認められる。
そうすると,亡A1は,遅くとも平成17年9月14日には,事理を弁識する能力に欠け,財産を管理することができない常況にあったと認められるから,このような状況下で同年10月12日に作成された本件公正証書遺言については,その当時亡A1が事理を弁識する能力を一時回復していたことが具体的に示されない限り,遺言能力がないために無効となるというべきである(民法973条参照)。
イ そのような見地から本件公正証書遺言が作成された状況を検討すると,まず,亡A1の遺言は公証人により作成されているが,公証人が遺言の作成に関与したということだけでは,遺言者に遺言能力があったはずであるとはいえない(同条参照)。
ウ そうすると,本件公正証書遺言の作成当時,亡A1には遺言能力がなかったと認められる。」
なお、この事案の遺言は、「全遺産を〜に相続させる」というとても単純な内容であり、これは遺言能力を肯定する一つの要因となり得る事情です。
しかし、この点についても、裁判所は、
「本件公正証書遺言の内容自体は,全財産を被告Y1に遺贈するという,単純なものであるが,そのような内容の遺言をする意思を形成する過程では,遺産を構成する個々の財産やその財産的価値を認識し,受遺者である被告Y1だけでなく,その他の身近な人たちとの従前の関係を理解し,財産を遺贈するということの意味を理解する必要があるのであって,その思考過程は決して単純なものとはいえない。」
と述べて遺言能力を否定しており、このような判断は特徴的といえます。
2016年1月4日更新