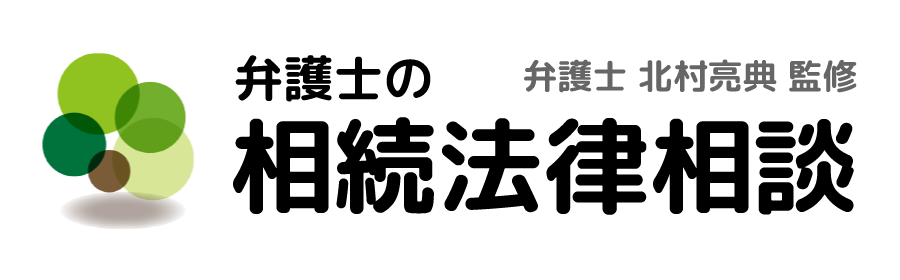Q 親が亡くなりました。
相続人は私と弟の二人だけです。
遺産は、親の住んでいた家・土地くらいしか有りません。
弟は、「家は処分してお金に変えて分けよう」と言ってきていますが、私としては先祖代々からある家・土地ですし、生まれ育った実家でもあるので、できれば売らずに自分がそこに移住して守っていきたいと思います。
その話を弟にしても「自分は売ってお金に変えたい。それが嫌なら兄貴がその分お金を払ってくれ」と言って聞きません。
この場合、遺産分割で私が家・土地を取得するためにはどうしたらいいのでしょうか?
A 代償金を支払うだけの資力があれば、代償金を払うのと引換に家と土地を取得することが可能です。
親が死亡し、その遺産が、親の住んでいた家と土地だけだったという場合、相続人である子どもたちの間では「もう誰も住まないのだから処分してしまおう。」という意見か、「せっかく親が住んできた家なのだから、処分せずに守っていきたい。」という意見のどちらかで争われることが多いです。
後者の意見、すなわち「親が住んできた家だから処分せずに守る。」という方向で遺産分割協議をする場合には、家と土地の名義を相続人全員の共有にするという遺産分割方法をとることもあります。しかし、これでは、解決を次の世代に先送りするだけになってしまいますので、あまり良い方法ではありません。
それよりも、むしろ家と土地を相続人のうちの誰か一人が取得することとし、不動産を取得した相続人は、他の相続人に対して各々の相続分の価値に相当する金額、すなわち代償金を支払うという遺産分割方法、すなわち代償分割という方法を検討することが一般的です。
この代償分割という方法をとる場合は、果たしてその代償金を支払うだけの能力があるのかどうかという点が重要です。
例えば、本件のケースで親の住んでいた家・土地が4000万円の価値がある一戸建てだった場合、それを取得したい兄は、弟に対して相続分の2分の1に相当する金額(2000万円)を支払われなければなりません。しかも、原則として一括払いです。
相続人間で意見がまとまらずに裁判となった場合には、代償分割の方法が認められるためには、代償金を支払うだけの能力があるかどうかについて、預金の残高証明書や銀行の融資証明書、売却予定の不動産の買付証明書などの財産の存在を証明する証拠を提出したり、事情の存在を主張しなければ、代償分割は認められません。
したがいまして、資力の証明というものがとても重要です。
【判旨:最高裁判所平成12年9月7日第一小法廷判決】
「家庭裁判所は、特別の事由があると認めるときは、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対し債務を負担させて、現物をもってする分割に代えることができるが(家事審判規則109条)、右の特別の事由がある場合であるとして共同相続人の一人又は数人に金銭債務を負担させるためには、当該相続人にその支払能力があることを要すると解すべきである。
これを本件についてみると、原審は、抗告人相沢順子に対し、原決定確定の日から6箇月以内に、相手方らに総額1億8822万円を支払うことを命じているところ、原決定中に同抗告人が右金銭の支払能力がある旨の説示はなく、本件記録を精査しても、右支払能力があることを認めるに足りる事情はうかがわれない。
そうすると、原決定には家事審判規則109条の解釈適用を誤った違法があり、右違法は裁判に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由があり、その余の点について判断するまでもなく、原決定中、被相続人楠木博文の遺産の分割に係る部分は破棄を免れない。そして、右に説示したところに従い更に審理を尽くさせるため、右部分について本件を原審に差し戻すのが相当である。」
2015年11月30日更新