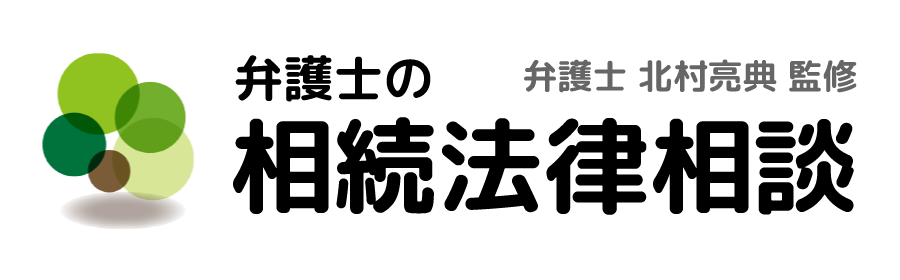【質問】
祖父が亡くなりました。
私の父は、既に亡くなっていたため、代襲相続人として祖父の遺産を相続することになりました。
私の父は亡くなるまで祖父の家業である農家に従事し、祖父のためにずっと働き財産の医事・増加に寄与していました。
私は、このような父の寄与を寄与分として主張したいのですが、それは可能でしょうか。
【説明】
親の家業や介護に尽くした者について、遺産分割の際に寄与分が認められるか?
という問題があります。
この問題については、主として、「その貢献が特別の寄与にあたるのか」「特別の寄与に当たるとして、寄与分としてどの程度の金額が認められるか」という点を巡って調停や審判で争われることが多いです。
しかし、その他の問題として、
「そもそも、寄与行為をした者が誰か?」
という点が問題となることがあります。
なぜかと言うと、民法は、寄与分を主張できる者を「相続人」に限定しています(民法904条の2)。
そうだとすると、特別の寄与(貢献)があったかどうかは「相続人」の行為について判断されるのであり、相続人以外の者がどれだけ貢献したとしても原則として遺産分割で寄与分は主張することはできないのです。
では、本件のように、寄与行為をした者が既に亡くなっており、その子が代襲相続人として相続する場合はどうでしょうか。
すなわち、被代襲者の寄与行為に基づき代襲相続人に寄与分を認めることができるか、という問題です。
本件は、東京高裁平成元年12月28日決定をモチーフにした事例です。
この事案で、裁判所は、
「寄与分制度は、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした相続人に、遺産分割に当たり、法定又は指定相続分をこえて寄与相当の財産額を取得させることにより、共同相続人間の衡平を図ろうとするものである」
とした上で、
「共同相続人間の衡平を図る見地からすれば、被代襲者の寄与に基づき代襲相続人に寄与分を認めることも、・・・許されると解するのが相当である。」
と判断しました。
このように、裁判所は、寄与分の制度趣旨から代襲相続人の主張を認めたものですが、これに加えて、代襲相続の制度趣旨からも認めることができます。
すなわち、代襲相続の効果は代襲相続人が被代襲者に代わって被代襲者の地位で相続することであり、被代襲者の相続分を受けることであり、代襲相続制度は被代襲者の死亡等による相続権の喪失で被代襲者の子が受ける不利益を避けて衡平を図るためのものであるから、代襲相続人が相続の効果として受ける内容は被代襲者の相続権と同一である、とされています。
したがって、被代襲者の主張できることは代襲者も主張できる、という帰結になるわけです。
2018年12月17日更新