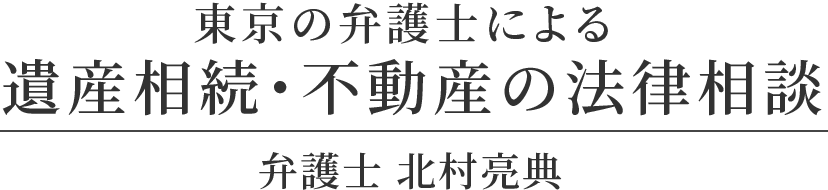遺産分割において、特定の相続人が生前贈与や学費の援助などを受けていた場合には、それが親族間紛争の原因になる場合があります。
このような生前贈与を遺産分割において考慮すべきか否かは、それが法的に“特別受益”として考慮すべきものに該当するか、また、それが客観的に証明できるものであるか、という点が重要です。
本記事では、特別受益の基本的な考え方と、それを遺産分割協議や調停でどのように立証するのかを解説します。
特別受益とは?
特別受益とは、民法903条に規定されている制度で、相続人の中の特定の者が被相続人から相続開始前に遺贈または贈与を受け、その受益が遺産分割における公平を害すると認められる場合に、その利益を相続財産に加算して計算するものです。
この場合の贈与や遺贈は、すべてが特別受益に該当するのではなく、特に「生計の資本」として提供されたものを指します。生計の資本とは、相続人が生活の基盤や大きな財産形成のために得た金銭や資産を指します。
具体的には、被相続人が相続人に対して以下の金銭等を生前に贈与していた場合が該当します。
特別受益の具体例
住宅の購入資金の援助:親が長男に自宅購入費として1,000万円を贈与。
学費の負担:親が長女の留学費用を全額負担。
事業資金の援助:親が次男に事業を始めるための資金を提供。
特別受益の立証が必要な場面とは
特別受益の主張が問題となるのは主に遺産分割協議や調停・審判の場面において、特定の相続人が、生前に被相続人から多額の生前贈与を受けていた場合、他の相続人はそれを遺産分割で考慮すべきであると主張する場合です。
この主張に対して、生前贈与を受けていた相続人が「自分は贈与など受けていない」などと反論をしてきた場合は、「特別受益があったこと」を主張する相続人がその存在を証明しなければならない、というのが遺産分割の裁判実務における基本的な考え方です。
このため、特別受益をどのように立証すべきかということが問題となるのです。
特別受益の立証方法
特別受益を主張する側は、それが実際に存在したことを証明しなければなりませんが、それは基本的には「客観的な証拠」で行う必要があります。このため、特別受益の存在を示す具体的な書類を集める必要があります。以下は代表的な例です。
贈与契約書:被相続人と相続人の間で正式に交わされた契約書。例:住宅購入費用を援助するために贈与契約を締結した場合、その内容と金額が記載されています。
銀行の振込履歴:被相続人が相続人の口座に直接送金した記録。例:特定の時期にまとまった金額が送金されている場合、その金額と用途が判断材料となります。
登記簿謄本:不動産が特定の相続人名義に変更されている記録。例:生前贈与として不動産が譲渡された場合、その所有権の移転記録が証拠となります。
領収書や契約書の控え:学費や事業資金に関する支出が分かるもの。例:留学費用を支払った領収書や事業資金の援助に伴う借用書など。
税務申告書:被相続人が贈与税申告を行っている場合、その申告書。例:大きな金額を贈与する際に贈与税が課税される場合、申告内容が重要な証拠となります。
注意点
特別受益の主張が認められるには、十分な証拠が必要です。証拠が不十分な場合、裁判所が特別受益として認定しない可能性が高いです。
そして、先述のとおり、特別受益の存在を主張する側がその証明責任を負います。そのため、準備不足のまま特別受益の主張をしても、結局は特別受益は認められませんので、いたずらに紛争が長引くだけの結果となってしまいます。
まとめ
特別受益の問題は、相続における相続人間の公平性を保つための重要なポイントです。しかし、その立証には具体的かつ明確な証拠が必要です。無用な紛争の長期化を避けるためには、過去の裁判例や弁護士からのアドバイスを具体的に参照しながら、遺産分割協議や調停の場で効果的に主張することが求められます。
この記事は、2025年1月19日時点の情報に基づいて書かれています。
この記事の監修者
北村 亮典東京弁護士会所属
慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。 現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。