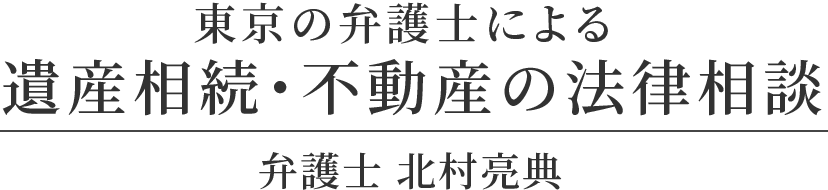親の介護を担当した家族が「その分を評価して多く相続したい」と感じるのは自然なことです。このような特別な貢献を考慮する仕組みが寄与分(きよぶん)というものです。
この記事では、寄与分の基本的な仕組みや計算方法、そして裁判例をもとに具体的な主張方法を分かりやすく解説します。
また、寄与分が認められる条件や具体的な金額の算出方法についても深掘りします。
寄与分とは?
寄与分とは、亡くなった方(被相続人)の財産を守ったり増やしたりするために特別な貢献をした相続人が、その貢献度に応じて法定相続分にプラスして相続分を得られるという制度です。これは民法904条の2で定められています。
寄与分が認められる例
– 親の事業を手伝い、大きく成長させた。
– 親の借金を代わりに返済した。
– 長年にわたり親の介護を行い、財産の減少を防いだ。
ただし、日常的な家事や通常の扶養義務の範囲内の行為は寄与分に該当しません。特に介護の場合、財産の維持や増加に繋がる「特別な貢献」と認められる必要があります。
寄与分が認められる基準
特に親の介護の寄与分が主張される場合、介護の苦労については、親の介護をしていた相続人と、そうではない相続人との間でその認識(介護に大変さなど)に相違がある場合が多く、親の生前に相続人間のコミュニケーションがしっかりと取られていない場合には、寄与分を巡って感情的な対立となってしまう場合があります。
寄与分について話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所での調停や審判を経て解決しなければなりません。
親の介護を理由に寄与分を主張する場合、次のポイントが重視されます。
介護の寄与分において重視されるポイント
1. 介護の期間と日数
– 介護を何年続けたか?(少なくとも1年以上の期間が必要とされています。)
–どのくらいの日数を費やしたか?
2. 介護の具体的内容
– 食事、排泄、入浴など、日常生活でどの程度の支援を行ったか?
– 外部サービスを利用せず、自宅介護を行ったか?
3. 財産への影響(無償で行われたか)
– 介護費用を自ら負担し、または無償で行い親の財産を守ったか?(無償で同居している親族に介護の場合は、無償で同居している対価として介護が行われたと評価され、無償での介護とはみなされない場合があります )
– 有料施設やサービスを利用せずに済ませ、財産の減少を防いだか?
4. 親の要介護度
-親の要介護度(要介護度は重要な考慮要素です。例えば、要介護1のように比較的軽度であれば相続人の負担も少ないとされる一方で、要介護5のような高い介護度の場合は、身体介助や日常生活全般の支援が必要になるため、特に大きな貢献として評価される傾向があります。)
寄与分の金額を計算する方法
介護の寄与分は、次の計算式で算出されることが多いです。
相当報酬額 × 療養看護日数 × 裁量割合
1 相当報酬額
相当報酬額は、介護保険制度の介護報酬基準を参考に決められることが一般的です。介護報酬は単位で表され、1単位の金額は地域区分によって異なりますが、基本的に1単位=10円とされています。
実際の介護報酬は、算定された単位数に地域区分ごとの単価を乗じて計算されますが、大まかな目安として、例えば、要介護3の利用者が7〜8時間のデイサービスを利用した場合、900単位×10円=9,000円が1日の介護報酬の目安となります。
2 裁量割合
裁量割合とは、寄与分の金額を調整するために用いられる係数です。通常0.5から0.8の範囲で設定され、平均的には0.7が使用されます。
なぜ、このような裁量割合が設けられるかというと、家族による介護は、有資格のヘルパーや看護師などのプロフェッショナルによる介護とは異なること、介護保険制度における介護報酬基準額をそのまま適用すると、家族による介護の評価が過大になる可能性があるためです。裁量割合は、この点を調整し、より公平な評価を可能にします
3 具体的な計算方法
以上を踏まえた寄与分の算定方法は、例えば、1日あたりの介護報酬相当額を8,000円、療養看護日数を300日、裁量割合を0.7とした場合:8,000円 × 300日 × 0.7 = 1,680,000円となります。
この記事は、2025年1月24日時点の情報に基づいて書かれています。
寄与分を主張する際に必要な準備
寄与分を認めてもらうためには、具体的な証拠が必要です。
収集すべき証拠
ⅰ 介護日記:介護の日程や内容を記録したもの。
ⅱ 医療記録:親の病状や通院の記録。介護認定における調査票。
ⅲ 領収書:介護にかかった費用を示すもの。
ⅳ 第三者の証言:ヘルパーや親戚による証言。
調停や審判となった場合、介護費用や労力が財産維持にどのように貢献したかを具体的に説明することが求められます。証拠は、裁判所に対して信頼性の高い主張を行うための鍵となりますので、できる限り生前から証拠の収集と整理をしておくことが望ましいです。
この記事の監修者
北村 亮典東京弁護士会所属
慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。 現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。