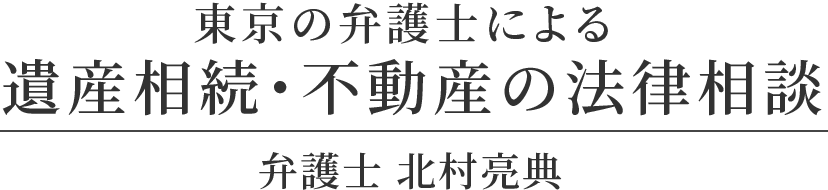ゼネコンや工務店に建物の建築を依頼し、建築請負契約を締結して建物を建ててもらったものの、その後に不具合が発見された場合、法律上は、
①瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求
②瑕疵の修理の請求
ができます。
この場合に一番問題となるのが、その不具合が「瑕疵」と評価されるかということです。
何か「瑕疵」にあたるか、という点について、仙台地方裁判所平成23年1月13日判決のケースは以下のように論じており、実務上参考となります。
1⃣ 請負契約における仕事の目的物の瑕疵とは、一般に、完成された仕事が契約で定められた内容を満たさず、目的物について、使用価値若しくは交換価値を減少させるような欠点があるか、又は当事者間で予め定められた性質を欠いているなど、不完全な点があることをいうものと解される。
2⃣ これを建物の建築工事請負契約に即してみると、建物としての機能や財産的価値の大きさなどに照らし、目的物である建物が最低限度の性能を有すべきことは、請負契約上当然に要求される内容といえるから、そのような最低限度の性能について定めた建築基準法令(国土交通省告示、日本工業規格、日本建築学会の標準工事仕様書(JASS)等を含む。)に違反する場合や、そのような違反がなくても当該建物が客観的にみて通常有すべき最低限度の性能を備えていない場合には、目的物について、契約で定められた内容を満たさず、使用価値若しくは交換価値を減少させるような欠点があるものとして瑕疵があるというべきである。
3⃣ また、建築物の建築工事実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書から成る設計図書(建築士法二条五項、建築基準法二条一二号)は、建築工事請負契約において定められた仕事の内容を具体的に特定する文書であることから、設計図書と合致しない工事が行われた場合には、その不一致がごく軽微であり、目的物の価値、機能及び美観などに影響を与えず、注文者の意思に反することもないといえるような特別の事情のない限り、目的物について、契約で定められた重要な内容を満たさず、当事者間で予め定められた性質を欠くものとして、瑕疵があるというべきである。
2015年12月14日更新
この記事の監修者
北村 亮典東京弁護士会所属
慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。 現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。