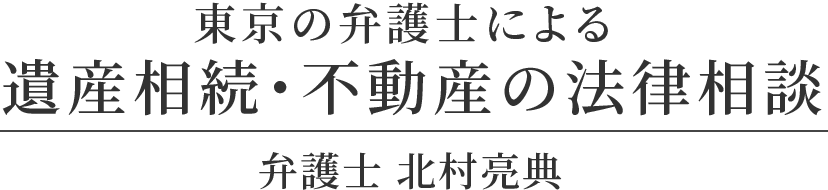1 不動産の賃貸借契約に消費者契約法は適用されるか
消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結される契約に適用されます。賃貸借契約の場合、賃貸人が法人ではなく個人のオーナーであったとしても、不動産の賃貸は継続的に収益を得ることを目的とした事業活動ですので、賃貸物件を所有し賃料収入を得ている時点で事業者とみなされます。
したがって、賃借人が個人で居住目的である限り、その賃貸借契約は消費者契約法の適用を受けることになります。
2 消費者契約法における違約金の制限について
消費者契約法の適用を受ける賃貸借契約において、違約金を設定する契約条項がある場合、消費者契約法9条と10条が適用されて、無効とされる場合があります。
まず、消費者契約法9条1項1号は、
①契約の解除に伴い違約金等を定める条項であって、②当該違約金等の額が、契約の解除に伴い生ずる平均的な損害の額を超える場合は、
③平均的損害を超える部分についてその違約金等条項を無効とする
と定めています。
したがって、賃貸借契約の解除に伴う違約金については、その平均的損害の額を超えるような定め方をした場合、これを超えた部分が無効と判断されてしまいます。
また、消費者契約法10条は、消費者の権利を制限し又は義務を加重する消費者契約の条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものを無効とする規定です。賃貸借契約における違約金条項についても、この規定の適用対象となる可能性があります。
3 賃貸借契約における違約金の設定
住居の賃貸借契約においては、
①賃借人が契約を中途解約する場合の違約金
②契約期間満了後(解除後)に明渡しが遅延した場合の違約金
が定められることが一般的です。これらの違約金について、消費者契約法が適用されるのか、また、適用される場合には消費者契約法違反とならないためにどの程度の違約金額であれば問題がないか、ということを検討する必要があります。
今回は、①賃借人が契約を中途解約する場合の違約金について、以下説明します。
4 中途解約の場合の違約金と消費者契約法の適用の問題
実務上よく見られるのは、「借主が1年未満で解約した場合,違約金として賃料の●か月分を支払う」とか「借主は、解約申入れの日から30日分の賃料を貸主に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。」といった条項です。
このような条項は、契約の解除に伴い違約金を設定する条項となりますので、消費者契約法9条1項1号が適用されます。
そうすると、このような条項における違約金の額が「契約の解除に伴い貸主に生ずべき平均的な損害の額」を超えないように契約書で設定をする必要があります。ここで想定される「契約の解除に伴い貸主に生ずべき平均的な損害」とは例えば、空室期間の家賃相当額や募集費用などと考えられます。
では、違約金の額として賃料の何か月分までが違約金として問題がないといえるでしょうか。
この点、国土交通省が公表している「賃貸住宅標準契約書」においては、賃借人からの中途解約条項において「解約申入れの日から30日分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。」と規定されています。
このため、一般的な個人の居住目的の賃貸借契約書の雛形では、違約金を1ヶ月間とする契約書も多く見られるところです。
もっとも、裁判例をみると見解が分かれており、この標準契約書が「一般的な契約条項のひな形を示したものに過ぎない」としたうえで
と述べている事例もあります。
他方で、
として1か月を超える分は消費者契約法9条1項1号に違反すると判断した裁判例もあります(東京簡易裁判所平成21年8月7日判決)。
以上を踏まえると、住宅の賃貸借契約においては、貸主が次の賃借人を募集して入居に至るまでに必要と考えられる期間、すなわち、違約金として設定しても問題ないと判断される賃料の期間は、1ヶ月であれば確実に問題ないといえ、2ヶ月とした場合は、中途解約によって2か月分の損害が発生することが見込まれる事情の存在を主張できるかどうかがポイントになるといえるでしょう。
この記事は、2025年3月13日時点の情報に基づいて書かれています。
この記事の監修者
北村 亮典東京弁護士会所属
慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。 現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。