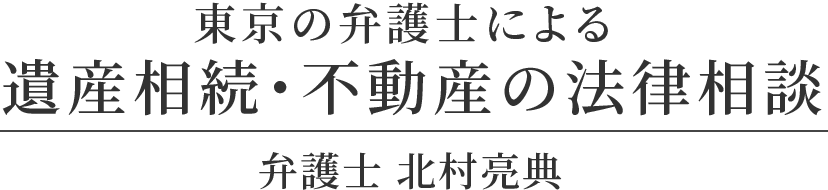【賃貸オフィスの借主からの相談】
私は、半導体や集積回路の設計開発・製造・販売を行う会社の代表をしています。
現在、平成18年1月から借りている、東京都千代田区にある賃貸事務所の立ち退きをオーナーから求められています。
賃貸物件は、地下鉄の駅からほど近い好立地にある7階建てのビルの一室です。ビル自体は昭和43年7月に新築されたもので、築47年以上が経過しており、新耐震基準前の古い建物です。
当社はこのビルの約11平方メートルの小さな区画を借りており、現在の賃料は月額4万3200円です。
契約当初はここを利用していましたが、現在は神奈川県川崎市に本社を構えています。そのため、この千代田区の賃貸物件は、本店とは別に「経営推進室」と称して都心での打ち合わせスペースや、重要なデータのバックアップ、契約書などの書類保管場所として利用しています。もっとも、一か月のうち5日~10日程度しか利用していない月が多いのも事実です。
このような状況下で、オーナー会社から「建物の老朽化と耐震性不足」を理由に更新を拒絶されました。オーナー側は、「立ち退き料として賃料の10ヶ月分に相当する43万2000円を支払うから明け渡してほしい」と主張しています。
確かに使用頻度は低いですが、都心の拠点を失うのは痛手ですし、データの移動や代替物件の確保には手間もかかります。たった40万円強の提示額で退去しなければならないのでしょうか。
老朽化の場合に立退きが認められる要件
本件のような建物賃貸借契約の更新拒絶が認められるかどうかは、借地借家法第28条が定める「正当の事由」の有無によって判断されます。
すなわち、借地借家法上、賃貸人(オーナー)が期間満了を理由に更新を拒絶するには、単に契約期間が終わったというだけでは足りず、「正当の事由」が必要とされています。この正当事由の有無は、以下の4つの要素を総合的に考慮して判断されます。
1.建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情(双方の必要性)
2.建物の賃貸借に関する従前の経過
3.建物の利用状況及び建物の現況
4.建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃貸人が財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出(いわゆる立退料の提供)
判例の結論は?
本件は東京地方裁判所の平成29年2月14日判決の事例をモチーフにしたものですが、本件の最大の争点は、オーナーが主張する「築約50年による老朽化・建て替えの必要性」と、テナント側の「データ保管場所や打ち合わせ場所としての必要性」の比較衡量でした。
特に、テナント側の実際の利用頻度が極端に低いという「建物の利用状況」が、正当事由の判断および立ち退き料の額にどう影響するかが重要なポイントとなりました。
裁判所は、結論として、オーナー側の請求を一部認容し、「オーナーがテナントに対して43万2000円(賃料10ヶ月分)を支払うことと引き換えに、建物を明け渡せ」という判決を下しました。
裁判所がどのような事実認定を行い、結論を導き出したのか、判決文を引用しながら解説します。
賃貸人側の自己使用の必要性
まず、オーナー側の「自己使用の必要性(建て替えの必要性)」について、裁判所は以下のように判示しました。
「本件ビルは、・・・築47年以上のもので、昭和56年の建築基準法改正による新耐震基準が施行される前に建築されたものであるところ、・・・極めてまれに起こる大地震(震度6強から7程度)においては可能性として危険な状況が想定されるとされ、かつ、部分的な補強は建物全体の耐震性バランスを崩すことから勧められないとして、上記程度の大地震に対応するには建て替えが合理的であると評価されている」
このように、建物の危険性と建替えの合理性を認める一方で、「上記定期建物賃貸借契約において,最も遅く契約が終了するもので,平成31年4月20日・・・である以上,少なくとも,それまでの間に,本件ビルの建て替え工事が開始されるということは考え難い」、「現時点で,新たに建築する建物がどのような規模になるのか,どのように利用するのかなど,具体的な計画があることを認めるに足りる証拠はない」と述べ、直ちに明け渡しを認めるほどの強い必要性まではないとも指摘しています。
つまり、オーナー側の事情だけでは、契約を終了させるには不十分であると判断されたのです。
賃借人側の使用の必要性
そこで本件で決定的な要素となったのが、テナント側の「使用の必要性」の低さでした。裁判所は、セコムの入退館履歴などに基づき、賃借人の利用実態を以下のとおり厳しく認定しました。
「被告は、平成25年8月から平成28年1月までの30か月間で,本件建物に現に入館して使用した日が10日以下である月が21か月,うち5日以下である月が11か月(平成27年10月においては,1日も入室していない。)であること,現実に入館した日の1日当たりの利用時間は10時間を超えることはほとんどなく,1時間に満たない日も相当の日数にのぼる」
そして、この事実認定に基づき、裁判所はテナント側の主張を次のように退けました。
「被告の代表者ないし従業員が本件建物に赴いて業務を行わなければ同社の業務の遂行が不可能になるということは到底いえず,むしろ,本件建物内で作業する必要性は非常に低いというべきである」
「現在は,本件建物があるからこれを打合せに利用することがあるものの,本件建物において打合せ等を行わないといけない必要性は非常に低いといわざるを得ない」
また、テナント側が主張した「データのバックアップや書類の保管場所」としての必要性についても、裁判所は以下のように述べて否定しました。
「セキュリティの確保された本社以外の場所であれば足りるのであり,本件建物のような,都心の中でも更に中心的な場所でなければならない理由は何もない」
「データのバックアップや書類等の保管という観点からも,本件建物を利用する必要性は非常に低いというべきである」
以上のように、双方の必要性を比較した上で、裁判所は
「原告側の使用の必要性が現状においてそれほど高いといえるわけではないが,それ以上に,被告側の使用の必要性が低いといわざるを得ない」
と双方の必要性の強弱について結論付けました。
オーナー側の必要性も弱いが、テナント側の必要性はそれ以上に弱い、という判断です。
立退料についての判断は?
以上の判断を踏まえ、立ち退き料について、以下の理由により、裁判所はオーナー側が提示した「賃料10ヶ月分(43万2000円)」を妥当と認めました。
「データのバックアップや書類保管のために代替物件を探すとしても本件建物と同等の立地である必要はないこと,本件建物の面積と所在している物に照らして,引越費用がそれほど高額になるとは考え難いことを併せ考えれば,上記金額の立退料があれば,本件更新拒絶の正当事由を補完するものとしては十分というべきである」
本事例の特徴
このように、本判決は、都心の一等地であっても、使用頻度が極端に低く代替性が高い利用状況であれば、比較的低額な立ち退き料で明渡しが認められる可能性があることを示しました。
本件は、賃借人の「実際の使用状況」を重視し、正当事由や立退料の金額を判断とした事例であるところ、本件のように、賃借人の利用実態が乏しい物件の場合、結果的に賃貸人側の提示額通りの低い金額で決着することも示したという点で参考となる事例です。
この記事は、2025年11月23日時点の情報に基づいて書かれています。
この記事の監修者
北村 亮典東京弁護士会所属
慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。 現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。