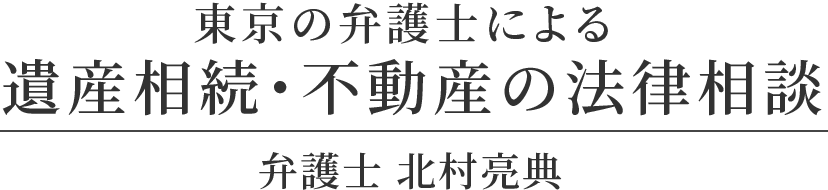1 賃料不払いによる契約解除の可否とその基準
賃貸住宅のオーナーの方々から賃借人との紛争で弁護士に相談される事案として多いものは、原状回復に関する紛争と賃借人の賃料不払いに関する紛争です。
賃料の支払い義務は、賃貸借契約における賃借人の義務として最も重要なものです。したがって、賃料支払い義務を誠実に履行しない賃借人に対して、賃貸人として契約の解除を求めることは至極当然の成り行きです。
しかし、賃料の不払いがあったからと言って、必ず契約の解除ができるというわけではありません。ここで問題となるのは、賃借人の賃料不払いを理由に貸主が契約解除を求めた場合であっても、「信頼関係破壊の法理」が適用されて解除が認められない場合もあるという点です。
すなわち、形式的に契約違反に該当したからと言って解除が認められるわけではなく、契約違反が当事者間の信頼関係を失わせる程度のものかどうか、という点でさらに検討を要することとなるわけです。
どの程度の賃料不払いであれば契約解除が可能となるのか、ということについて、裁判実務では原則として「賃料の不払いが合計3か月分に達した時点」で信頼関係破壊により解除が可能という基準が概ね確立されています。
しかし「3か月分の賃料不払いで解除可能」というのは、あくまでも信頼関係破壊の一つの基準であり、その他の事情を考慮して、賃料不払いが3か月未満でも解除を認めたり、逆に賃料不払いが3か月に達していても解除が認められなかったという裁判事例もあります。以下では、2か月分の賃料滞納で解除が認められた裁判例(東京地裁平成29年5月25日判決(平28(ワ)8799号))を紹介します。
2 事案の概要
本件は、東京都内の建物について、賃貸人である原告が賃借人である被告に対し、月額賃料93,000円、管理費20,000円、その他費用を含め合計約117,567円で賃貸していた事案です。保証人として全保連株式会社が保証契約を締結していました。
紛争の発端は、被告が管理費月額2万円が賃料に比して高額であることを問題視したことにあります。被告は、平成27年4月の水道修理において業者が約束の時間に来なかったことや即日修理が完了しなかったこと、さらに平成28年4月のインターネット工事で管理会社のミスにより誤った鍵を渡され工事ができなかったことなどを理由に、管理費を月額1万円に減額するよう一方的に要求しました。そして、被告はこの減額について原告の了承を得たと主張するようになったのです。
そして、被告は、平成27年9月分から、管理費1万円を一方的に減額した月額約107,567円のみを支払うようになりました。この不足分については保証会社が毎月代位弁済することとなり、被告は保証会社からの求償に対しても、保証会社ではなく原告の口座に振り込むなど不誠実な対応を続けていました。
この状況が平成27年9月から平成28年1月まで5ヶ月間継続した後、ついに被告は平成28年2月分と3月分の2ヶ月分を完全に支払わなくなりました。これを受けて原告は平成28年3月11日付けで解除通知をしたのです。
3 裁判所の判断
本件の争点
この事案では、
①管理費減額合意は存在したか
②信頼関係が破壊されたと言えるか
の2点が争点となりました。
管理費減額の合意の成否
まず、裁判所は、被告が主張する管理費減額の合意について詳細に検討し、その存在を否定しました。
理由としては、結局のところ、被告代表者の供述以外に減額合意を裏付ける客観的証拠は何も存在しなかったためであり、裁判所は管理費減額の合意があったとは認められないと結論付けました。
信頼関係破壊の有無
次に信頼関係破壊の有無について、裁判所は、平成28年3月14日の解除通知到達時点で、すでに賃貸人と賃借人の間の信頼関係が破壊されていたと判断しました。
この判断の根拠として裁判所が重視したのは、被告が5ヶ月間にわたって継続的に約定に違反し続けたという事実です。支払時期を守らず、一方的に減額した金額しか支払わず、保証会社への対応も不誠実であったという一連の行為は、単なる金銭的な債務不履行を超えて、契約関係の基礎となる信頼を損なうものでした。
さらに裁判所は、被告が法的根拠のない管理費減額要求を執拗に継続し、原告が応じる義務のない要求に固執し続けたことを「原告に対する法的な責任を超えた不当な要求行為」と認定しました。これは単に賃料を滞納したという以上に、賃貸人と賃借人の関係性そのものを破壊する行為として評価されたのです。
そして最終的に2ヶ月分を完全に滞納したことが、すでに損なわれていた信頼関係に決定的な打撃を与えたと判断されました。
なお、本件賃貸借契約には、賃借人が賃貸人に対する法的な責任を超えた不当な要求行為を行ったときは、何らの催告も要せずして直ちに契約を解除できるという無催告解除特約が定められていました。
裁判所は、被告の一連の行為がまさにこの特約に該当すると認定し、原告による催告なしでの解除を有効と判断しました。これは、被告の行為が単なる債務不履行を超えて、契約関係の継続を困難にする背信的行為に該当することを明確に認めたものです。
4 まとめ
本判決は、賃料滞納による契約解除において、形式的な滞納月数だけでなく、賃借人の態様や経緯を総合的に考慮すべきことを明確に示しています。「3ヶ月分の滞納」という一般的な基準は確かに存在しますが、それはあくまで一つの目安に過ぎません。賃料不払いに加えて、賃借人が不当な要求を繰り返したり、一方的な減額を継続したりするような行為があった場合、その行為と合わせて信頼関係を破壊の有無を判断し、契約解除事由として評価される可能性があることを本判決は明確に示しています。
賃貸人としては、賃料不払いで紛争となっている賃借人がいる場合、契約解除を確実にするためには、交渉の経過などで賃借人の問題となる行動を証拠化しておくということが重要です。例えば、電話内容の録音や、少額入金や支払い日の遅延の正確な記録、メールやLINEなどのやり取りの保存です。これらの記録があることで、単なる賃料滞納の月数だけでなく、賃借人の悪質性や背信性を立証でき、より確実な契約解除へと繋がります。
この記事は、2025年9月28日時点の情報に基づいて書かれています。
この記事の監修者
北村 亮典東京弁護士会所属
慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。 現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。