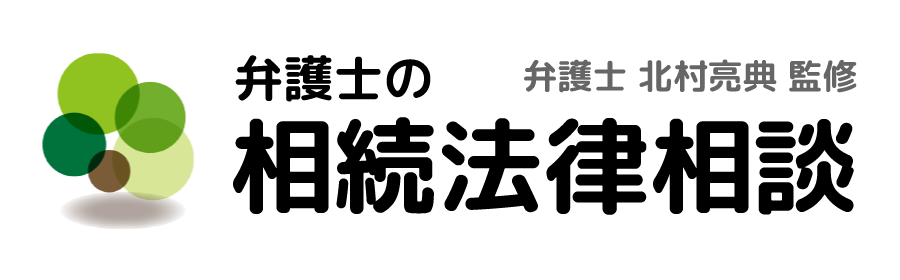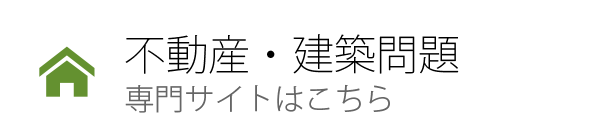遺留分の請求方法
父が亡くなったので、相続人の長男と次男が遺産分割の話し合いをしようとしていました。すると、長男は「父の遺言がある」と言って、「全財産を長男に相続させる。」という遺言を出してきました。このような遺言書がある場合、次男の相続はどうなるのでしょうか?
遺留分とは
相続人が長男、次男の二人であれば、法定相続分は各2分の1ずつとなります。しかし、民法が定める法定相続分というのはあくまでも遺言のない場合の相続人の相続分を規定するものに過ぎず、遺言がある場合には遺言の内容が優先となります。
したがって、この場合は、遺言の内容に従い、長男が全財産を相続し、次男は何も相続できない、ということとなります。これでは、次男からすれば、「自分も相続できたはずなのに・・・」という期待をまさに裏切られたこととなってしまい、次男にとっては酷な話となってしまいます。
この次男の相続に対する期待を実現するための手段として、法律上「遺留分」という権利が定められています。遺留分というものは、相続人に最低限認められている権利です。この権利は、遺言によってもそれをゼロにすることはできません。「遺留分」という権利が認められる理由は、相続人の相続に対する期待の保護と、被相続人の財産の処分自由の原則との調整を図るため、と言われています。
遺留分についてもっと詳しく
遺留分の請求の必要性
もっとも、冒頭のケースのような遺留分を侵害するような遺言がなされていたとしても、その遺言が直ちに無効となるわけではありません。遺留分を侵害された者が、何も言わずに1年間放っておくと遺言書の内容がそのまま確定してしまいます。そこで、遺留分を侵害された相続人は、まず第一に、遺留分を侵害する贈与(遺贈)を受けた者に対して、遺留分に相当する金銭又は不動産の所有権持分を請求する必要があります。この請求を法律上「遺留分侵害額請求」といいます。なお、2019年7月1日以降に発生した相続の場合は、金銭の請求のみが認められます。
遺留分の請求方法
遺留分減殺請求は、1年間という厳格な期間制限があり、期間を経過してしまうと一切請求できなくなってしまいますので、期間内にまずは請求する意思があることを明らかにしておかなければなりません。
また、この1年間という期間内に請求したかどうかという点が後に裁判となった場合に争われることもありますので、これを後々証明できるように請求しなければなりません。
具体的には、以下の手順で請求することが一般的です。
1. 内容証明郵便による請求
まず、内容証明郵便で相手方に対して「遺留分減殺請求権を行使する」という内容の書面を送ることが第一です。内容証明郵便で遺留分の主張をした後は、まずは相手方との話し合いで、遺留分に相当する金額を払ってもらうか、もしくは不動産の持分をもらうかなどの交渉をすることとなります。しかし、相手が交渉に応じない場合は、裁判所での手続による解決を目指すこととなります。
2. 「調停」(家庭裁判所での話し合い)
裁判所での手続には2種類あり、「調停」と「訴訟」があります。
調停とは、簡単に言うと、裁判所の人(この人のことを「調停委員」といいます)が間に入って話し合いの場を作り、話し合いによる解決を目指す手続です。調停委員は、両方の意見を聞きながら、法律的にも妥当で双方が納得するような和解が成立するよう尽力します。ここで、和解が成立すれば全て終了します。
しかし、調停とは既に述べたとおりあくまでも「話合いによる解決」を目指す手続ですので、解決のためには合意が必要です。
どちらかが話し合いに応じなかったり、調停委員が間に入って和解案を提示しても、どちらかが首を立てに振らなければそれ以上調停を進めることはできません。
このような場合には、調停手続は終了します。
なお、事前の交渉で、そもそも話し合いでの解決の見込みが全くないというような場合は、調停手続を行わず、以下3の訴訟に踏み切る、というケースもあります。
3. 「訴訟」(裁判を起こす)
調停が不調となった場合に、白黒をつけるためには、遺留分を主張する者が裁判所に「訴訟」を起こす必要があります。
「訴訟」とは、双方が自分の主張とそれを裏付ける証拠を裁判所に提出し、裁判官がその内容を踏まえて、請求を認めるか、棄却するかの「判決」を言い渡すという手続です。
「訴訟」は「調停」とは異なり、話合いではなく裁判所が主張と証拠に基づいて強制的に判断を下すという手続ですので、話合いが不調であっても必ず何らかの形で結論が出されることとなります。
もっとも、「訴訟」の手続の中でも、裁判官が「判決」となった場合の見通しを述べつつ和解による早期の解決を目指すということもあります。