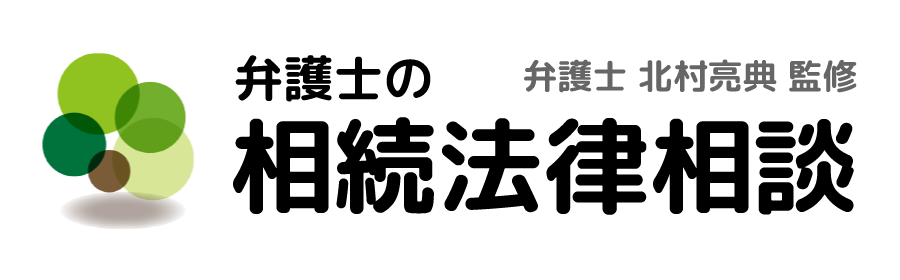【質問】
私の叔父が亡くなりました。
叔父は、夫も子供もいなかったため、その妹である私の叔母ふたりと私の母が相続人となったのですが、私の母は既に亡くなっているため、私が代襲相続人として相続人の一人となっています。
生前の叔父の面倒や死後の葬儀の取りしきりなどは、全て叔母のうちの一人がやっていたため、その叔母からは「遺産は全て私が相続したいからあなたの相続分を譲渡してもられないか」という連絡が来ました。
私としては、その叔母に相続分を譲渡しても良いと考えていますが、相続分の譲渡とはそもそも何なのでしょうか。
【説明】
1 相続分の譲渡とは
相続分の譲渡とは、
「積極財産のみならず消極財産を含めた遺産全体に対して各共同相続人の有する包括的相続分、あるいは法律上の地位」を譲渡するもの
というのが法律の解釈です。
言い換えれば、「相続人としての地位」を全て譲り渡すもの、ということが言えるでしょう。
この相続分の譲渡は、有償でも無償でも可能ですし、どのような方式で行っても良いとされています。
実務上は「相続分譲渡証書」というものに署名・実印を押印して行われるのが一般的です。
また、相続分の一部のみを譲渡することも可能ですし、相続人以外の者(第三者)に対して譲渡することも可能です。
相続分の譲渡と比較されるのが、相続放棄という制度ですが、相続分の放棄と比べても上記のように相続分の譲渡の方が色々と柔軟な対応が可能です。
ただし、相続分の譲渡が可能なのは「遺産分割協議の成立前」となっており、遺産分割が成立した後に行うことはできないとされています。
また、後述のように、相続分の譲渡には借金の放棄までの効果はありません。
2 相続分の譲渡の効果
相続分の譲渡がなされると、譲渡人の相続分が無くなり、譲受人にその相続分が全て移転します。
例えば、相続分の譲受人が、共同相続人の1人である場合には、譲受人本来の相続分に、譲渡した人の相続分が加わることになります。
相続分の譲渡は積極財産と消極財産の双方を譲渡するものではありますが、しかし、相続債務(被相続人の生前の借金)があった場合、相続分の譲渡をしても、この責任は免れることはできない、ということとなっていますので、この点は注意が必要です。
実務的には、相続分の譲渡をした場合は、相続分を譲り受けた人が責任を持って相続債務の弁済にも対応しますが、万が一、債権者から相続分の譲渡をした人に請求が来てしまい、支払わざるを得なかったような場合には、その後に相続分の譲渡人から譲受人に対して返済した分の求償をするということになります。
3 相続分譲渡後の遺産分割について
相続分を譲渡した後は、相続人としての地位は無くなり、相続財産に関する権利を一切失うことになります。
そのため、その後に、譲受人その他の相続人間で遺産分割協議や調停を行う事となった場合も、相続分を譲渡した者はその協議・調停に加わる必要はない、ということになります。
実務上は、相続分譲渡後に遺産分割調停が行われるような場合、家庭裁判所は、譲渡の事実を明らかにするため、譲渡人からの相続分譲渡届出書及び印鑑登録証明書の提出を促すとの運用がされています。譲渡届出書が提出されると、裁判所が排除決定を行い、相続分の譲渡をした共同相続人は遺産分割手続の当事者ではなくなります。
また、相続分の譲受人は、譲受人が第三者の場合(相続人ではなかった場合)であっても、その後の遺産分割協議に参加すべきこととなります。
したがって、譲受人が第三者であった場合、この者を参加させずになされた遺産分割協議の効力は無効となります。
4 相続分の譲渡を後から取り消すことはできるか
相続分の譲渡は、法律的には、譲渡人と譲受人との間の「契約」ということができます。
したがって、一旦譲渡が成立した後でも、譲渡人と譲受人の合意があれば解除することができます。
また、仮に、相続分の譲渡をした後に、譲渡人が預かり知らない事情により高額の遺産が発見されたなどの事情が生じた場合、そのような高額な遺産があることを知っていれば相続分の譲渡をしなかったであろう、ということであれば、錯誤により無効になる可能性もあります。
5 共同相続人の取戻権
相続分の譲渡は、相続人以外の第三者に対しても行うことが可能です。
しかし、この場合、残された相続人は、この第三者である譲受人を加えて遺産分割協議をしなければならないということとなり、これはケースによっては遺産分割協議が円滑に進行しないおそれがあります。
そこで、民法は相続人の取戻権(民法905条)というものを認めています。
民法905条
1 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
この取戻権を行使した場合には、償還のための価額・費用を負担した相続人に、その相続分が移転します。
この記事は2021年7月25日時点の情報に基づいて書かれています。