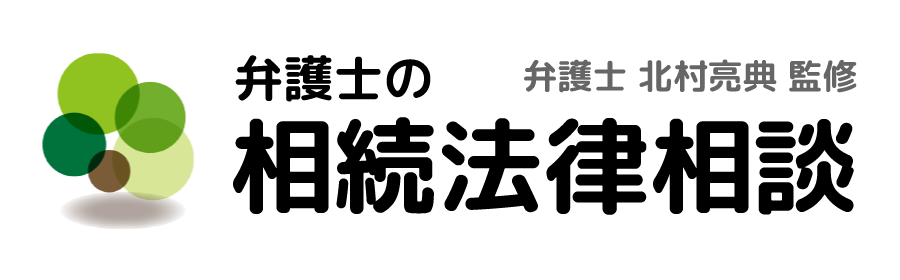公正証書遺言であっても、後にその遺言の効力が遺言無効確認訴訟で争われることがあります。例えば、
・遺言書を作成した当時、親が重度の認知症だった
・遺言書を作成したのが、重病で入院中で、しかも死亡した日の一週間前だった
という場合、遺言書によって不利益を受ける相続人にとっては、その遺言書は
「本当に親の意志でつくられたものなのか?」
と納得できない気持ちに駆られることは避けられないですよね。
そうなると、この遺言書が有効か無効かを法的に争うという事態にも発展していきます。
裁判所が、その遺言書が有効なのか、無効なのかを判断するにあたっては、
遺言書を作成した当時、遺言者に「遺言能力」があったかどうか
という点を中心に審理します。
この「遺言能力」とは、遺言書を遺す者が、遺言の内容をしっかり理解できるだけの知的判断能力、を言います。
したがって、遺言能力が争われるケースとして多いのは、遺言書の作成当時に認知症と診断されていた高齢者が遺言を作成していた場合です。
また、認知症ではなかったとしても、重篤な病の治療・投薬等の影響で衰弱し、精神状態にも異常が生じていた場合なども、遺言能力がないと判断されることがあります。
東京高等裁判所平成25年8月28日判決のケースは、認知症の高齢者ではなく、癌の鎮痛剤等の薬剤の影響で精神状態に異常をきたしていた高齢者が作成した公正証書遺言を無効としました。
このケースは、遺言者が、末期癌の対症療法・緩和療法を受けるため入院し、それから間もなくして病院で公正証書遺言が作成され、さらにその6日後に死亡した、という事例です。
このケースで、裁判所は
①Aは,進行癌による疼痛緩和のため,病院より麻薬鎮痛薬を処方されるようになり,病院に入院した後は,せん妄状態と断定できるかどうかはともかく,上記の薬剤の影響と思われる傾眠傾向や精神症状が頻繁に見られるようになったこと
②本件遺言書作成時の遺言者の状況も,公証人の問いかけ等に受動的に反応するだけであり,公証人の案文読み上げ中に目を閉じてしまったりしたほか,自分の年齢を間違えて言ったり,不動産を誰に与えるかについて答えられないなど,上記の症状と同様のものが見受けられたこと
③本件遺言の内容は,平成22年1月時点での遺言者の考えに近いところ,遺言者は,同年7月に上記考えを大幅に変更しているにもかかわらず,何故,同年1月時点の考え方に沿った本件遺言をしたのかについて合理的な理由は見出しがたい
ということを理由にして、遺言書作成当時,遺言能力がなかったと判断しました。
この事案では、遺言者の病室に公証人が赴き、そこで公正証書が作成されたのですが、その際の事実経過が判決では細かく認定されています。
例えば、
「遺言公正証書作成の際のやりとりは,基本的には,公証人が,同案文に沿って誘導的な質問をし,被相続人が(酸素マスクを装着したまま)「うん」あるいは「ああ,はい」等の声を発するという形で進められた。」
「このやりとりの中で,被相続人は,不動産を誰に取得させるかとの旨の質問に対しては,当初「春野」と答えるなどし,その後,公証人の誘導的な質問が繰り返された後,くぐもった声で「春野,一郎」と聞こえる名を挙げた。また,事前に用意されていた公正証書遺言の案文を被相続人が見ながら,公証人が読み上げをすることが予定された場面では,被相続人は,すぐに目を閉じてしまった。」
「さらに,被相続人は,年齢を聞かれ,明らかに実際とは異なる年齢(57歳や67歳)を答えるなどした。なお,公証人からは,他に,肯定か否定で答えられないような質問も格別なされず,また,被相続人の方からも,積極的に何か言うこともなかった。」
と認定されています。
ここまであからさまに公証人と遺言者とのやりとりが判決上認定されていることは驚きではありますが(公証人が証言したのでしょうか)、遺言者の心身の状態はかなり悪かったことは容易に窺われ、遺言能力の欠如に裁判所が傾くのも至極当然のように考えられます。
このような経緯が認定されたとなれば、遺言書を無効と訴えている遺族側からすれば、無効にならなければ全く納得できないでしょう。
本件は、認知症ではなかった高齢者の公正証書遺言無効事例として、また重病で病に伏していた方が死の直前に作成した公正証書遺言について無効にした事例として、参考になると思われます。